こんにちは、こころ社労士事務所の香川昌彦です。
去る令和7年6月28日、愛知学院大学で開催された日本口臭学会第16回学術大会にて「職場における口臭を含む臭いマネジメントとメンタルヘルスへの配慮(Managing Workplace Odors Including Halitosis with Sensitivity to Mental Health)」というテーマで、講演を行いました。
臭いの問題はとてもデリケートで、なかなか話題にしづらいものですが、職場で働くみんなが心地よく過ごすためには、適切な理解と対応がとても大切というのがコアメッセージです。
以下、講演の内容を簡単にまとめました。
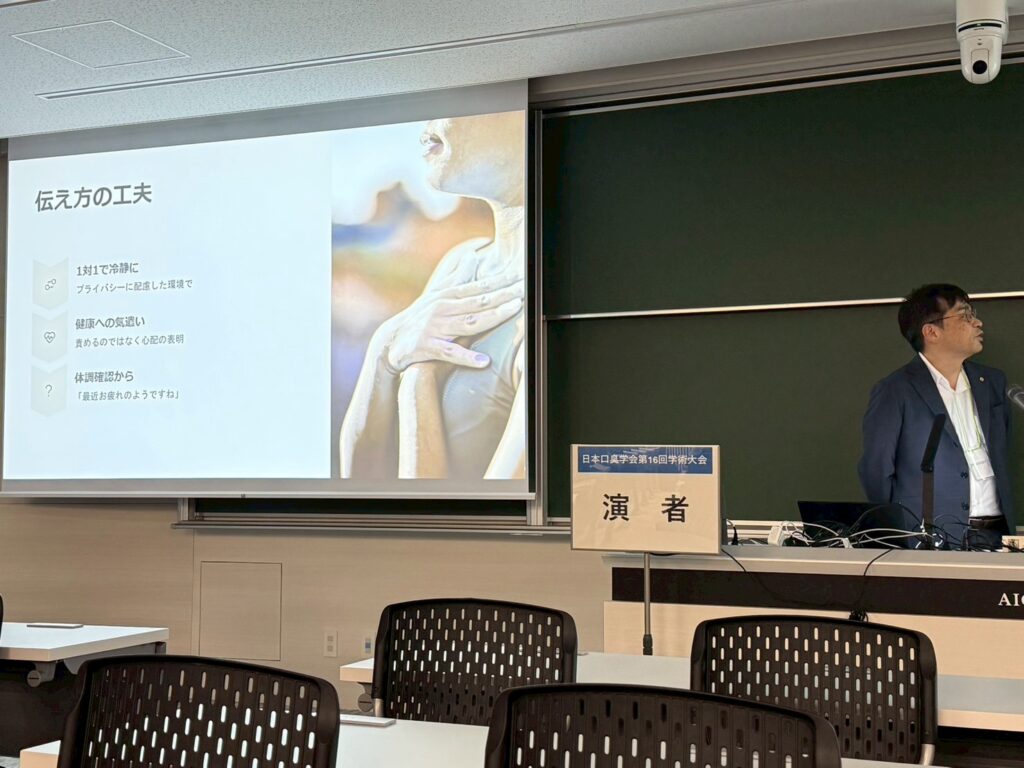
「臭い」は誰にでも起こりうるサイン
職場では、「口臭が気になるけれど本人に言いづらい」「指摘したら逆に責められてしまった」という悩みが少なくありません。ですが、臭いの問題の多くは、本人に悪意があるわけではなく、体調や心の不調のサインである場合も多いのです。
たとえば、ストレスや睡眠不足、心の不調によってセルフケア(歯磨きや入浴など)が難しくなり、口臭や体臭が強くなることがあります。これは「清潔感がない」と片づけてしまうべきものではなく、「何か助けが必要なのかもしれない」という視点で捉えることが大切です
臭いは困った人の「迷惑な行動」や「本人の清潔感のあるなしの問題」ではなく、何かのサイン”として受け止めることが大切なのです。
「スメハラ」と「ハラスメント・ハラスメント」
最近では、臭いの問題が「スメルハラスメント」として注目されがちですが、すべてが法的なハラスメントに当てはまるわけではありません。必要以上に相手を責めたり、指摘自体をタブー視しすぎると、逆に新しいハラスメント(ハラスメント・ハラスメント)を生み出してしまうこともあります。臭いの問題に蓋をすることで、より臭いの問題を深刻化させているという側面があります。
誰かを責めたり排除したりする視点ではなく、「どうしたら皆が快適に働けるか」を一緒に考えることが臭いの問題については求められます。
伝え方にもやさしさを
臭いの問題を伝える際には、1対1のプライバシーが守られる場で、相手を思いやる言葉を選ぶことが重要です。たとえば、「最近、体調はいかがですか?」と健康への気遣いから話を始めると、お互いに傷つけ合うことなく、本当の意味でのサポートがしやすくなります。
また、上司や同僚が伝える場合でも、決して一人で抱え込まず、職場全体でフォローできる体制が必要です。伝える側がプレッシャーを感じたり孤立したりしない配慮が求められます。
職場ぐるみの仕組みづくりが安心感に
臭いの問題は個人だけの責任にせず、職場として制度や環境づくりが大切です。たとえば、健康相談窓口の設置や、歯科検診へのサポート、定期的なストレスチェックなどを活用し、「困ったときに声を上げやすい」「健康について気軽に話せる」雰囲気をつくることが、結果的にみんなの安心感や働きやすさにつながります。
まとめ
臭いの問題は「マナー」や「清潔感」だけでなく、その人の心や体調、環境の変化にも目を向けることが大切です。「この人に元気に働き続けてもらいたい」という思いやりを忘れずに、互いに支え合える職場が増えていくことを願っています。
臭いだけに限らず、職場でのあらゆる事象をハラスメントとする風土が職場を窒息させます。お互いを思いやり、みんなで良い職場環境を創ることがなによりも大切なのです。

こころ社労士事務所は、働く人一人ひとりの気持ちや状況に寄り添ったご相談・サポートを大切にしています。職場の人間関係やメンタルヘルスでお悩みの方は、どうぞお気軽にご相談ください。

